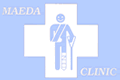 |
医院案内|地図|診療案内|症状からみる病名チェック|役立つ医学情報・Q&A|趣味の部屋| リンク | 無料健康相談掲示板| お問い合せ |
|
| 役立つ医学情報・Q&A |
| ●腰痛の方のための日常生活上の注意点 |
| ●腰痛の方のための腰にやさしい座り方 | ||
| ●あなたの腰痛は、かがむと痛い腰痛? そると痛い腰痛? |
| ●スポーツ医学による筋力トレーニングのリハビリメニューへの導入 |
| ●膝・腰・肩の部位別トレーニング方法 |
| ●テニス肘について |
| ●テニス肘について 【原因】 肘のところの、上腕骨には、親指がわと小指側に2つの突出部がありますが、それぞれ内上顆(手のひらを天井に向けたときに肘の小指側の突起)、外上顆(肘の突起の親指側)とよばれています。 内上顆には屈筋群(指や手首を手のひら側に曲げる)や回内筋郡(手のひらを顔の方へ向ける筋肉)がついています。 外上顆には回外筋(手の甲を顔に向ける動作の筋)や手・指の伸筋郡(指や手首をのばす)がついています。 テニス肘といわれる病態は、この関節外の骨膜部とそこに付着する腱の炎症と考えられています。 また腱を構成する繊維の過度使用による部分断裂も考えられています。 最もよく起こる原因としてテニスがあげられるので、一般的にテニス肘といわれます。ゴルフでも起こることがあり、ゴルフ肘ともいわれることがあります。 一般的にテニス肘といわれるのはテニスのバックハンドで痛めるもので、外上顆の障害です。バックハンドでテニスボールを受ける際20kgほどの衝撃があるといわれており、それに耐え手首を一定の位置に固定するために伸筋が収縮し外上顆部の筋腱付着部への負担が生じ発症します。医学上の診断名は上腕骨外上顆炎といいます。これがバックハンド・テニスエルボーです。 またフォアハンド・テニスエルボーの医学上の病名は上腕骨内上顆炎といわれます。 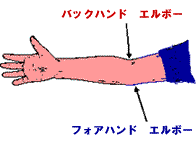 【症状】 肘の関節そのものには、痛みも、曲がらないなどの機能障害もないのですが、腱の付着部の緊張を増強させるような場合に強い痛みを感じます。時に自発痛や前腕へ走る痛みが出ることもあります。 雑巾を絞ったり(この場合左手では内上顆部に負担がかかり、右手では外上顆部に負担がかかる)、バックハンド・テニス肘の場合ビールを注ぐときなどに外上顆部に痛みを覚えます。 【治療】 バックハンドテニス肘の場合、指をのばしたり手首を手の甲側に反るような力を加えないようにすることが大事です。 フォアハンドテニス肘の場合、手のひらを曲げるような力を加えないように注意します。 場合によっては手関節副子を使用して固定することもあります。 痛みが強いときは局所麻酔薬とステロイドホルモンの注射をしたり、消炎鎮痛剤や湿布を使用したりします。 リハビリでは症状を有する筋郡のストレッチングをおこなったり、SSPなどの電気治療を行います。痛みの軽減に伴って筋力増強を追加し症状の再発防止をおこないます。 【予防】 ①運動の前後は温熱と冷却を必ずおこないましょう。運動前は15分間の温熱パック、運動後は15分のアイシングです。 また、テニス肘用サポーターの着用も有効です。テニス以外でも着用をおすすめします。 ②筋力をつける 1〜2キロ程度の鉄アレイをゆっくり持ち上げる動作を1日10回おこないます。筋力トレーニングは、痛みがある時期におこなうとかえって症状が悪化してしまうので、必ず痛みがとれてからおこなってください。 ③ラケットは柔らかいものを 自分に合ったラケットを使い、正しいフォームを身につけ、ラケットの中心でボールをとらえることで肘への負担は小さくなります。硬いラケット、重いラケット、強いガットテンションは肘への負担が大きくなります。 ④ストレッチは非常に効果的 リハビリには、筋力トレーニングとストレッチをおこないます。これらは、再発防止にも効果があります。 【右肘がテニス肘の場合】 まず、右腕を前伸ばして、手のひらを下に向け、指先を左手で持ち、手前に引っ張るように手首を曲げます。静止30秒×3回。→ 伸筋のストレッチ、外上顆炎の場合。 次に、右手のひらを上に向け、左手で指先を持ち、手前に引っ張るように手首を曲げます。静止30秒×3回。→屈筋のストレッチ、内上顆炎の場合。 痛みが強いとき以外は、慢性で痛みを感じているときでもおこなってください。 |
||
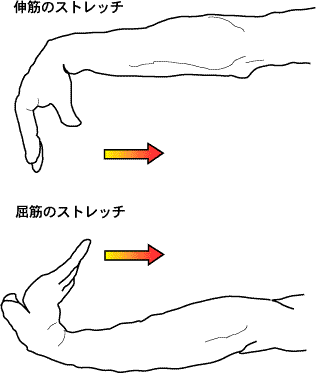 |